まんなか冷凍まとめ
更新日:
2025/7/3

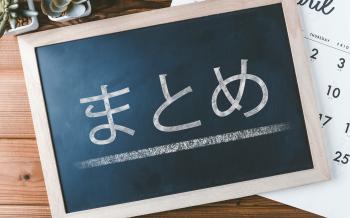
冷凍機能にこだわった日立《まんなか冷凍》が注目を集める。その特徴とライバル製品との違いを比較してみた。
目次
- 1: まんなか冷凍の分かりやすい解説
- 2: まんなか冷凍のメリット・デメリット
- 3: まんなか冷凍のライバルは?
- 4: ふもとあさとの読むラジオ
まんなか冷凍の分かりやすい解説
《まんなか冷凍》の概要
日立の冷蔵庫シリーズ「まんなか冷凍」は、冷凍室を中央に配置することで、使いやすさと保存性能を両立させた製品です。食材のまとめ買いや作り置きをする家庭に特に適しています。
主な特長
- 冷凍室が中央にあることで、出し入れしやすく、整理しやすい構造。
- デリシャス冷凍機能により、食材を素早く冷凍し、うまみと栄養素を保持。
- 霜ブロック機能で霜の発生を抑え、食品の品質を保つ。
- まるごとチルドで冷蔵室全体がチルド温度になり、ラップなしで保存可能。
- 新鮮スリープ野菜室により、約10日間野菜の鮮度を維持。
- 冷蔵庫カメラ機能で庫内の状況をスマホで確認でき、買い忘れを防止。
環境への配慮
- 冷却システムの独立化で省エネ設計。
- 再生プラスチックを部品に使用。
- ノンフロン冷媒採用で環境負荷を軽減。
対象ユーザー
- 食材をまとめ買いする方
- 冷凍保存や作り置きを重視する方
- 外出先で庫内を確認したい方
- 環境に配慮した家電を選びたい方
まんなか冷凍のメリット・デメリット
《まんなか冷凍》のメリット・デメリット
メリット
- 腰の高さで使いやすい冷凍室が“まんなか”にあることで、かがまずに出し入れでき、日常使いに便利。
- 整理しやすい3段ケース食材を種類ごとに分けて収納でき、奥まで見渡しやすい構造。
- 高性能な冷凍技術「デリシャス冷凍」「霜ブロック」などにより、食材の鮮度と品質をしっかり保持。
- 家族全員が使いやすい子どもや高齢者でもアクセスしやすく、共同利用に適している。
- スマホ連携で庫内確認冷蔵庫カメラ搭載モデルでは、外出先から庫内を確認でき、買い忘れ防止に効果的。
デメリット
- 冷凍室の容量が制限される場合がある中央配置のため構造上の制約があり、下段タイプより容量が少ない可能性もある。
- 冷蔵庫全体の省エネ性に影響冷凍室の配置により冷却効率が下がることがあり、一部モデルでは消費電力量が高めになる。
- 重たい冷凍食品の収納に注意引き出し式構造により、大型や重たい食材の収納には工夫が必要。
- 掃除がやや面倒な場合も複雑な引き出し構造では、パーツの取り外しや清掃に時間がかかることもある。
向いているユーザー
- 冷凍食品や作り置きをよく使う方
- 家族で冷凍室を共有することが多い方
- 腰をかがまずに利用したい方
- スマートに食材管理をしたい方
まんなか冷凍のライバルは?
《まんなか冷凍》のライバルと比較による特徴解説
ライバル製品
ニトリ「まんなか切替冷凍冷蔵庫」は、冷凍室を中央に配置した3ドア冷蔵庫で、「変温室」搭載による柔軟な温度設定が可能。
《まんなか冷凍》の優位性
- 冷凍性能に特化「デリシャス冷凍」や「霜ブロック」により、食材の鮮度保持と霜対策が優れている。
- 整理しやすい3段ケース冷凍室が3段構造で、食材の分類・収納がしやすい。
- スマホ連携冷蔵庫カメラ搭載モデルでは、冷蔵・冷凍・野菜室をスマホから確認可能。
- 保存機能の充実「まるごとチルド」や「新鮮スリープ野菜室」により、ラップなし保存や長期鮮度保持が可能。
ニトリ製品との比較
- 変温室による柔軟性約-18℃〜+5℃まで1℃刻みで温度調整可能。
- 冷凍容量の拡張性変温室を冷凍室に切替えることで、最大136Lの冷凍スペースに。
- 価格の違いニトリは約7万円前後のリーズナブル価格。まんなか冷凍は機能性に応じて価格に幅がある。
比較表
- 冷凍性能:まんなか冷凍は高性能、ニトリは汎用性重視
- 整理性:まんなか冷凍は3段ケース、ニトリは変温室による柔軟収納
- スマホ連携:まんなか冷凍は対応、ニトリは非対応
- 保存機能:まんなか冷凍はチルド・野菜室が高性能、ニトリは微凍結に対応
- 柔軟性:まんなか冷凍は専用設計、ニトリは温度調整で多用途
- 価格帯:まんなか冷凍は中〜高価格、ニトリは低価格
ふもとあさとの読むラジオ
 あさと
あさと
さぁ、ここからはスタジオに戻ってきました。ふもとあさとです。いや〜、《まんなか冷凍》、聞けば聞くほど便利そうですねぇ。リンリン、特に印象に残ったポイントはどこでしたか?
 琳琳
琳琳
やっぱり、冷凍室が“まんなか”という発想はユニークですよね。よく使う場所が腰の高さにあることで、出し入れがとても楽になりますし、3段ケースで整理しやすいのもポイントです。
 ロン
ロン
ワンワン!ご指名ありがとうございます、ふもとさん。《まんなか冷凍》のデリシャス冷凍は、アルミトレイを活用して熱伝導を高め、食品の細胞破壊を抑えることで品質を維持する工夫がされています。これは家庭用としてはかなり高水準ですね。
こちらもおススメ♪
















