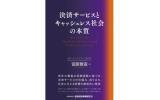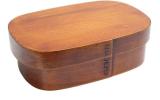ショアジギングロッドの選び方とメリット・デメリット
更新日:
2025/5/18

ショアジギングロッドは、遠投性能や耐久性を兼ね備え、釣りの幅を広げてくれる重要なアイテムです。本記事では、初心者から上級者まで役立つロッド選びのポイントとメリット・デメリットを詳しく解説します。
目次
- 1: ショアジギングロッド比較
- 2: ショアジギングロッドの選び方、ポイントまとめ
- 3: ふもとあさとの読むラジオ
ショアジギングロッド比較
ショアジギングロッドの良い点(メリット)
- 遠投性能が高い
ショアジギングでは、沖の魚を狙うために遠投が必須です。ショアジギングロッドは長めの設計が多く、強靭なブランクス(竿の素材)とガイド配置により、遠くまでルアーを飛ばすことができます。 - 高い耐久性とパワー
青物(ブリ、ヒラマサ、カンパチなど)や大型魚とのファイトに耐えるよう、強度が高く設計されています。カーボン素材の最適な組み合わせにより、しなりとパワーのバランスが取れています。 - 多様なルアーに対応
メタルジグ、ミノー、トップウォーターなど、さまざまなルアーを扱える設計になっており、狙う魚種や釣り場に合わせた釣りが可能です。 - 価格帯が幅広い
エントリーモデルから高級モデルまで、予算に応じて選べるため、初心者から上級者まで幅広く対応できます。
ショアジギングロッドの悪い点(デメリット)
- 重さがある
強度を確保するためにブランクスが厚めで、全体的に重くなりがちです。長時間の釣行では腕に負担がかかりやすく、疲れやすい点が難点です。 - 取り回しが難しい
長尺ロッドが多いため、狭い場所では扱いにくいことがあります。特に岩場やテトラポッド周辺では、キャスト時に周囲の障害物に注意が必要です。 - 初心者には扱いづらいことも
竿の長さや硬さにより、キャストのコツをつかむまでに時間がかかることがあります。また、適切なリールやラインとの組み合わせが必要で、セットアップに手間がかかる場合もあります。 - 価格が高めのモデルも多い
高品質なモデルは3万円以上することもあり、初心者にはハードルが高いと感じるかもしれません。
ショアジギングロッドの選び方、ポイントまとめ
ショアジギングロッドの選び方
- ロッドの長さ
ショアジギングでは、遠投性能を考慮して9~11フィート(約270~330cm)のロッドが一般的です。長いほど飛距離が伸びますが、扱いにくくなるため、釣り場の環境に合わせて選ぶのがポイントです。 - ロッドの硬さ(パワー)
ロッドの硬さは「ML(ミディアムライト)」「M(ミディアム)」「MH(ミディアムヘビー)」などの表記で示されます。- ML~Mクラス:小型青物やライトショアジギング向き。扱いやすく初心者にもおすすめ。
- MH~Hクラス:大型青物向き。強度があり、重たいジグも使用可能。
- 対応ルアーウェイト
ロッドには推奨されるルアーの重さが設定されています。- 軽め(20~40g):初心者向けでキャストしやすい。小型青物を狙うのに適している。
- 重め(60~120g):大型魚や深場狙いに向いている。遠投性能が高い。
- ロッドの素材
主にカーボンやグラスファイバーが使われます。カーボンは軽量で感度が良く、グラスファイバーは耐久性に優れます。最近はカーボン+グラスの複合素材も人気です。 - グリップの種類
- ストレートグリップ:力強いキャストが可能。長時間の釣行に向いている。
- セパレートグリップ:軽量でコンパクト。持ち運びや操作性に優れる。
- ガイドの種類
ガイド(糸を通す部分)はステンレス製とSiC(セラミックコーティング)製があり、SiCは耐摩耗性が高くPEラインとの相性が良い。よりスムーズなライン放出が可能。 - 持ち運びや収納性
- 1ピースロッド:継ぎ目がなく強度が高いが、長いため持ち運びに不便。
- 2ピースロッド:持ち運びや収納しやすく、釣行時の利便性が高い。最近は性能が向上し、人気が高まっている。
ショアジギングロッド選びのポイント
- 初心者は「M~MH」「30~50g」対応のロッドを選ぶと扱いやすい。
- 遠投したい場合は「10フィート以上」「60g以上対応」のモデルを選ぶ。
- 狙う魚のサイズに合わせて硬さ(パワー)を選ぶ。
- 収納・持ち運びを考慮するなら「2ピースモデル」が便利。
- PEラインを使うなら「SiCガイド」採用モデルがおすすめ。
ふもとあさとの読むラジオ
おすすめ商品ランキング
- 参照(4)
こちらもおススメ♪